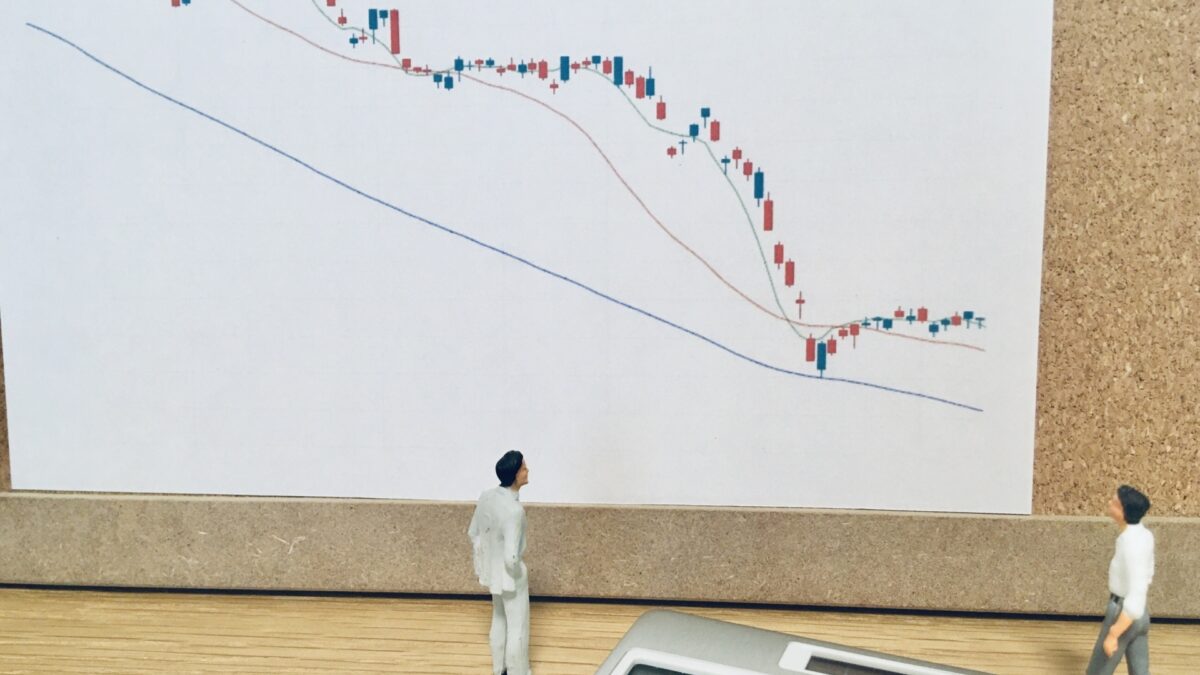長年にわたり苦境が続いていた電動トラックメーカーのニコラ(NASDAQ: NKLA)が、2025年2月中旬に劇的な株価変動を見せた。
2月18日には、日本の野村ホールディングス(TYO: 8604)が第4四半期の持株比率を9.3%まで引き上げたことが報じられ、同社の株価は一時40%以上急騰した。
しかし、その翌日、ニコラは連邦破産法第11章(チャプター11)の適用を申請する方針を発表し、プレマーケットで46.94%の大幅下落となった。かつてテスラの競合と目されていた同社の転落は、EV業界全体の厳しい環境を浮き彫りにしている。
ニコラの破綻が示すEV業界の限界と事業モデルの課題

ニコラの破綻は単なる経営の失敗ではなく、EV市場そのものが抱える構造的な問題を浮き彫りにしている。同社の歩みを振り返ると、特に事業モデルの脆弱性が露呈していたことが分かる。
ニコラは創業当初から「水素燃料電池とバッテリーの両方を搭載する電動トラックの開発」に注力するとしていた。しかし、技術的な確立には時間を要し、市場の期待に応えられなかった。
さらに、収益源の多様化に失敗したことも大きな要因である。テスラがエネルギー事業やソフトウェア収益を確保しているのに対し、ニコラはトラックの販売に依存していた。これにより、開発遅延や市場の変動が直接財務に影響を及ぼし、事業の持続可能性を確保できなかった。
また、水素燃料に関するインフラ整備の遅れも同社の計画に影を落とした。水素ステーションの不足により、ニコラのトラックは実用性に疑問符が付けられた。結果として、顧客企業の導入が進まず、販売計画は大幅に未達となった。
EV市場が成長する中でも、ニコラのように技術と事業戦略が合致しない企業は苦境に立たされる。今回の破綻は、事業モデルの柔軟性が欠ける企業にとって、市場の変動が致命的な影響をもたらすことを示している。
EV市場の成長鈍化が与える今後の影響
ニコラの破綻は、EV市場が持続的な成長を遂げるとするこれまでの見方に疑問を投げかける。EVシフトが進むとされる中で、需要の低迷やコストの上昇が課題となっている。
特に、米国政府の補助金政策の見直しは市場の成長に大きな影響を及ぼす可能性がある。バイデン政権下ではEV推進策が積極的に進められたが、2025年に入り政策転換の兆しが見え始めている。補助金が減少すれば、消費者のEV購入意欲が低下し、市場全体の成長が鈍化するリスクが高まる。
また、バッテリーの原材料価格の上昇も業界の負担となっている。リチウムやコバルトなどの主要資源の価格変動が続いており、特に中国との貿易摩擦が長引けば、供給網の不安定化がさらに深刻化する可能性がある。
EVメーカーにとって、今後は単なる車両販売に頼るのではなく、電動モビリティ全体のエコシステムを構築することが求められる。テスラがエネルギー事業を拡大し、フォードやGMが充電インフラの整備に取り組むように、新たな収益モデルの確立が不可欠となるだろう。
EV市場の成長が鈍化する中で、各企業がどのような戦略を打ち出すかが今後の業界の動向を左右する。特に、政策や市場環境の変化に対応できない企業は、ニコラと同様の道をたどる可能性がある。
EV市場は成熟期に入るのか、それとも新たな局面へ?
EV市場の成長が鈍化している今、業界が成熟期に入ったと捉えるか、新たな技術革新の転換点と見るかで今後の展開は大きく異なる。
一つの見方として、EV市場は「初期の急成長を終え、次のステージに移行した」とする意見がある。普及率が一定の水準に達し、新規参入企業の淘汰が進んでいるのは自然な流れとも言える。
しかし、EV市場はまだ発展の余地を十分に残している。特に、バッテリー技術の革新が進めば、航続距離の向上やコスト削減が可能となり、消費者の需要は再び高まる可能性がある。また、自動運転技術や充電インフラの進展も市場拡大のカギを握っている。
さらに、商用EVや水素燃料電池車の市場は、今後の成長が期待される分野である。ニコラが直面した課題を克服する新たな企業が台頭すれば、EV市場は次の成長サイクルに入ることも考えられる。
EV市場が一時的な停滞にあるのか、それとも新たな局面に突入するのかは、今後数年の技術革新と政策の動向にかかっている。
Source:Finbold